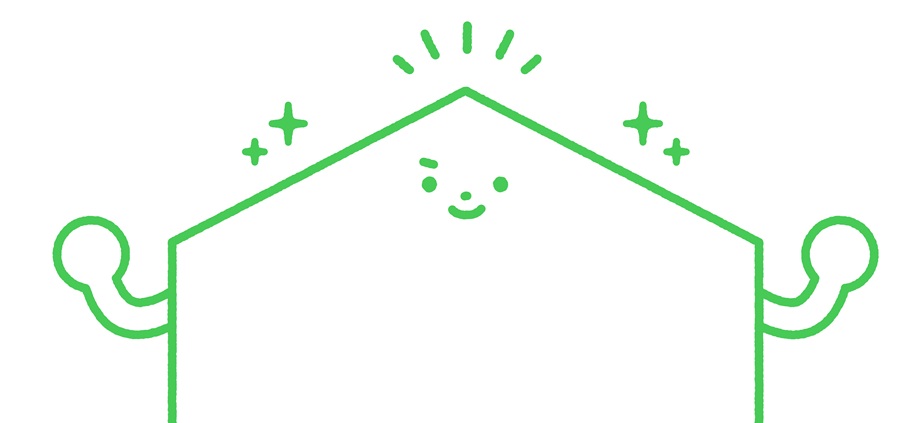「親の土地に新しい家を建てれば、土地代が浮いてお得」。そう考えて計画を進める方は少なくありません。
けれども実際には、境界の曖昧さや共有名義、相続の整理不足といった“見えにくい壁”に直面し、計画が進まないケースが多いのも現実です。
ここでは、40代のM様ご夫婦(小学生のお子様2人)が実家の敷地に家を建てる際に直面したリアルな悩みをもとに、親の土地に家を建てるときの事前チェックポイントをお伝えします。
後悔しないために知っておきたい3つポイント
・境界を“曖昧なまま”にしないことの重要性
・共有名義と民法上の同意ルールを理解する
・「解体」から「建築」までに潜む落とし穴
「実家だから大丈夫」と思ったら大間違い
M様ご夫婦が最初に直面したのは、実家の敷地境界が曖昧だったことでした。
実家の周囲には古くからのブロック塀や植木が境界のように見えましたが、役所で確認すると「法的な境界線は未確定」とのこと。
さらに調べると、土地の一部が親戚との共有名義になっていることも判明。「うちは親の土地だから大丈夫」と思っていた計画が、一気にストップしてしまったのです。
名義のあいまいさが工事を止めるリスク
それでも何とかなると楽観視していたM様。
しかし工務店からは、「境界が不明確なまま工事をするとトラブルのもとになる」と指摘を受けました。
・隣地との境界があいまい → 塀を壊したら「うちの塀まで壊された」と言われるリスク
・共有名義のまま → 民法上、共有地に新しい建物を建てるには共有者全員の同意が得た方がよい
つまり、建築確認申請そのものは通っても、民法上の権利関係で建築工事がストップする可能性があるのです。
“名義”と“相続”の落とし穴
M様がさらに頭を悩ませたのは、相続登記の問題でした。
土地の名義はご両親のまま。将来相続が発生した場合、5歳上の姉と、3歳下の妹と共有することになり、今建てた家が「共有地の上にある」という複雑な状態になるリスクがあります。
実際には多くの方が親名義のまま家を建てますが、その場合でも「将来相続が発生したときにどう整理するか」を今のうちに家族で話し合っておくことが重要です。
M様が選んだ選択肢
最終的にM様ご夫婦は、
・境界確定測量を実施し、隣地との合意を取り付ける
・共有名義の土地を親戚と話し合いの上、解決する
・親や兄弟姉妹と話し合い、将来の相続方法を共有してから計画を進める
というプロセスを踏むことにしました。
当初の予定より数か月遅れ、費用も増えましたが、「将来子どもに負担を残したくなかった」と振り返ります。
マッチングコーディネータの視点!
「親の土地に家を建てたい」と希望される方は多いですが、実際にご相談を受けると 境界・共有名義・相続 の3点で止まってしまうケースが非常に多いのが現実です。
工務店との打ち合わせに入る前に、
・境界は確定しているか?
・土地の名義は誰か?
・共有者全員の同意は得られるか?
・相続後の整理をどう考えるか?
この4点をクリアにしておくことが、安心して家づくりを進める第一歩です。
図面や間取りの前に「土地と権利関係の整理」を優先することが、後悔しない秘訣といえるでしょう。