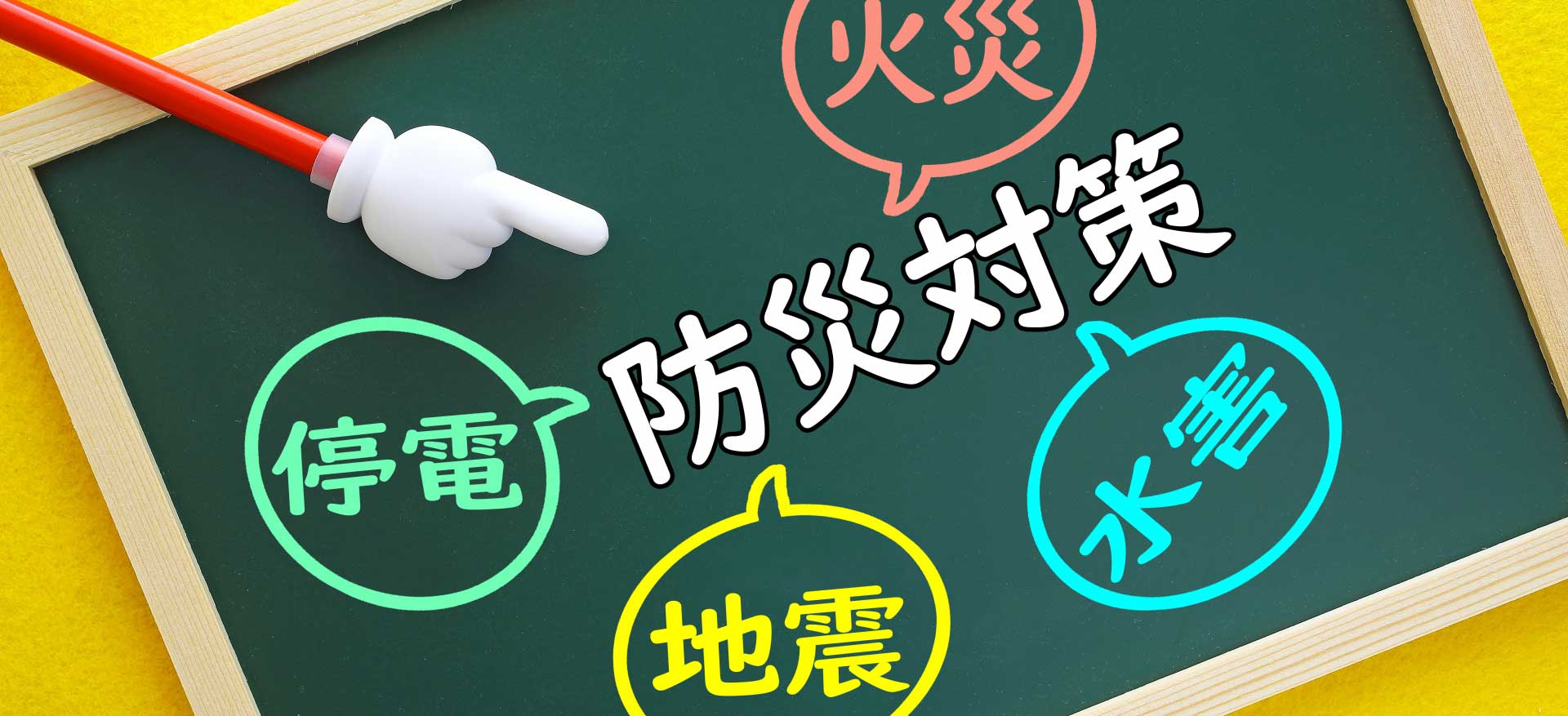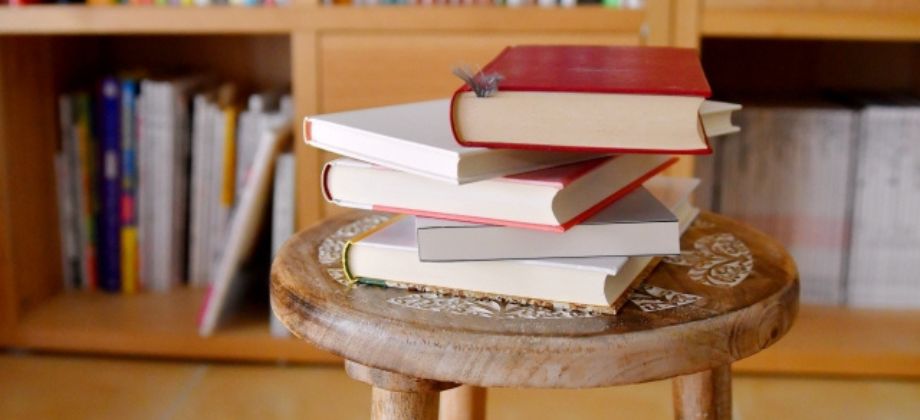便利な立地で価格も手頃な土地。しかし、ハザードマップを見ると「浸水想定区域」に入っている。そんな状況で迷う方は少なくありません。今回は、実際にハザードマップを確認して不安を抱えたS様ご一家の事例をもとに、注文住宅を建てる前に知っておきたいリスクと対策の考え方を整理します。
知っておきたいポイント3つ!
・ハザードマップの正しい見方と注意点
・浸水リスクに対する住宅の備え方
・「土地を変える」か「対策を強化する」かの判断基準
希望どおりの土地だけれどハザードマップが・・・
S様ご一家(夫婦+中学生1人)は、職場や学校へのアクセスが良く、価格も予算内の土地を見つけました。しかし、市役所で確認したハザードマップには「想定最大浸水深 1.5m」の表示。
「もし本当に浸水したら生活はどうなるのか」「設備強化でどこまで安全にできるのか」と不安が広がり、購入をためらっていました。
ハザードマップの意味すること
ハザードマップは“危険だから住めない”を意味するものではありません。
あくまで「災害が発生した場合の最大想定」を示すもので、自治体によって更新頻度や基準が異なります。
S様の場合、まず現地を確認し、以下を調査しました。
・過去の浸水履歴(自治体の防災課や地元の聞き取り)
・土地の標高や周辺の排水計画
・避難経路と避難所までの距離
その上で、「建築での備え」と「土地選びの見直し」の両方のシナリオを比較しました。
●建物での浸水対策
高基礎工法:床下浸水を防ぎ、設備の被害を軽減
排水ポンプ・逆流防止弁:大雨時の水の逆流を防ぐ
生活インフラの高所設置:給湯器・分電盤を床上1m以上に配置
●土地自体を見直す
ハザードマップで安全度の高いエリアに移動
同等条件の土地と比較して将来の資産価値も検討
●情報と行動の備え
自治体の防災メール・アプリを登録
家族で避難計画を事前に共有
非常用持ち出し品の準備
S様は最終的に、当初の土地に高基礎+排水設備強化を組み合わせたプランを選びました。理由は、立地の利便性と土地価格のバランス、そして「対策すれば十分暮らせる」と判断できたためです。
工務店の提案で分電盤を1.8mの位置に設置し、給湯器も高所へ。さらに、家族全員の避難ルートを事前に確認し、防災グッズを常備しました。「災害への不安が、行動に変わった」とS様は語ります。
マッチングコーディネータの視点!
ハザードマップは土地選びの重要な判断材料ですが、「避ける」だけでなく「備える」選択肢もあることを知ってほしいです。実際には、災害対策を前提にした設計でリスクを下げながら、便利な立地を確保する方も多くいます。重要なのは、リスクを正しく理解し、納得できる形で家づくりに反映させることです。リスクを数字と地図で把握すれば、冷静に「備える」か「避ける」かの判断ができます。