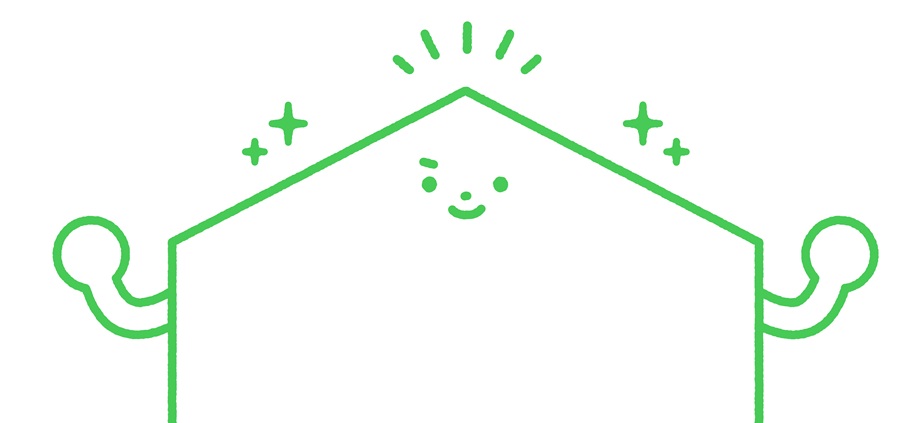「大きな地震が来ても、本当に安心できる家にしたい」。
注文住宅を検討される方から、そんな声をよく聞きます。
今回ご紹介するのは、地震への不安から耐震性能に強くこだわりたいH様ご夫婦(40代)のケース。耐震等級や制震ダンパーといった言葉は耳にするものの、工務店ごとに推奨する仕様が異なり、「どこまで必要なのか?」という疑問が大きな悩みとなっていました。
知っておきたいポイント3つ!
・耐震等級3は“最低限”の基準かどうか
・制震ダンパーなどの費用対効果
・地盤調査・地盤改良の重要性と判断軸
耐震等級3は本当に“安心の目安”?
H様ご夫婦は、ハウスメーカーや工務店に相談するたびに「耐震等級3だから安心です」と説明を受けました。確かに耐震等級3は現行制度上の最高ランクで、建築基準法の1.5倍の強さを持つとされています。
ただし実際には、
- ・等級3でも「簡易な壁量計算のみ」で済ませる場合がある
- ・構造計算(許容応力度計算)を実施しているかで精度が大きく異なる
といった“見えない差”が存在します。ポイントは「等級3を取得しているか」だけではなく、「どの計算方法で等級3を証明しているか」です。
制震ダンパーは入れるべき?
次に悩んだのが制震ダンパーの有無です。
工務店によっては「必須」と言われたり、「コストに見合わない」と否定されたり、判断が揺れました。
制震ダンパーの特徴は:
- ・繰り返しの地震動を吸収し、建物の損傷を軽減する
- ・初期コストは数十万円〜百万円単位で上乗せ
- ・地盤条件や建物形状によって効果に差が出る
費用対効果を考えると、“耐震等級3+構造計算(許容応力度計算)”が前提にあって、その上で余力があれば検討するものと整理するのが現実的です。
地盤調査と改良、どこまで必要?
H様が最後まで悩んだのは、地盤改良の判断でした。
- 表層改良(地盤を固める工事)
- 鋼管杭やコンクリート杭の打設
これらは地盤調査の結果によって選択されます。ただし、調査方法や判定基準も工務店によって差があり、「ある会社では改良不要と言われたが、別の会社では地盤改良を勧められた」というケースも実際にあります。
ここで大事なのは、第三者の解析やセカンドオピニオンを取ること。地盤は一度失敗するとやり直しがきかず、最終的な建築コストに大きく影響します。
H様が選んだ答え
最終的にH様ご夫婦は、
- ・耐震等級3を構造計算(許容応力度計算)付きで確認
- ・制震ダンパーは、後付けも技術的には可能だが大掛かりな工事になるため、
- 「今の予算と安心感のバランス」で導入を見送る判断
- ・地盤改良は地盤解析専門会社の意見も取り入れて判断
という形を選びました。
「“全部盛り”にするのではなく、根拠を持って取捨選択できたことが安心につながった」と話していました。
マッチングコーディネータの視点!
これまでの相談で多いのは、「等級や装置の名前は知っているけど、優先順位が整理できない」というケースです。
工務店に確認すべきは:
- ・等級3を「どの計算方法」で証明しているか
- ・制震ダンパーは標準かオプションか、その費用対効果はどうか
- ・地盤調査の判定根拠は何か
さらに、2025年4月の法改正で「4号特例」が縮小され、木造2階建て住宅は壁量計算だけでは建てられず、構造安全性に関する審査が必須となります。一方で、延べ200㎡以下の木造平屋住宅については、従来どおり壁量計算等で安全性を確認すれば建築が可能です。
耐震は「法律でどこまで必要か」と「家族がどこまで安心したいか」、この両面で判断することが大切です。不安を抱えたまま工務店任せにせず、自分の優先順位を整理してから相談に臨むことが、納得できる家づくりへの近道です。