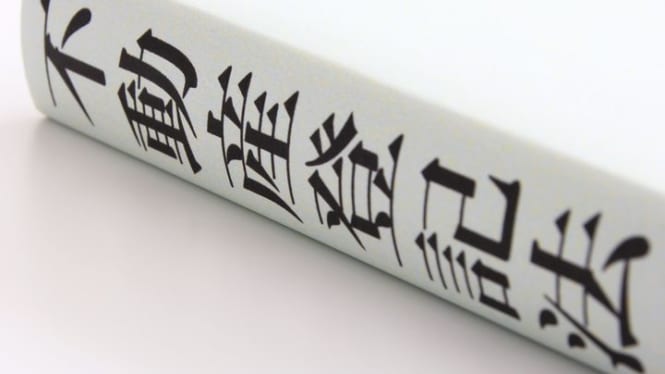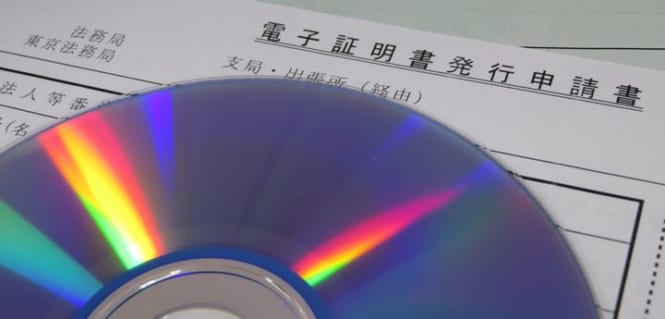取得の方法
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)は、誰でも取得することができます。
戸籍謄本や住民票は個人的な情報ですので取得が制限されていますが、不動産の登記情報はそもそも自分以外の人に権利内容を知ってもらうためのものですので、誰でも手に入れることができます。
登記簿謄本を取得する場合には、土地の「地番」と建物の「家屋番号」が必要です。「地番」や「家屋番号」は登記簿上の住所のようなものですが私たちが日常に使っている住所とは異なる場合があります。登記済証(いわゆる権利証)や登記識別情報通知書,固定資産税に関する課税明細書等で「地番」や「家屋番号」を確認してください。
これらが分からない場合は、法務局に備え付けられているブルーマップで確認するか、窓口で質問してください。
登記簿謄本取得の方法は3つあります。
オンラインを利用して取得
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局の登記・供託オンライン申請システムを利用してオンラインにて請求することができます。なお、交付は、郵送または窓口受取となり、電磁的な登記事項証明書等がオンラインで交付はされません。
オンラインで登記簿謄本の交付請求をする場合は以下のような手順となります。
1.法務局のサイトに申請者情報を登録する
2.登記事項証明書の申請書を作成し、送信する
3.手数料を納付する
4.登記簿謄本を窓口か郵送で取得する
オンライン請求した際にかかる手数料は、受け取り方法が窓口か郵送かによって異なります。一時利用として利用する場合は、クレジットカード決済となります
法務局で取得
法務局の窓口で、登記簿謄本を取得することが可能です。
必ずしも各市区町村毎に法務局はあるわけではありませんので、法務局のサイトで最寄りの法務局をご確認ください。
法務局ごとに、管轄している不動産は決まっていますが、法務局もオンライン化され、最寄りの法務局でも遠方の不動産の登記簿謄本も取得可能です。
法務局を訪れ申請書を記入し、登記印紙を申請書に貼って窓口に提出します。登記印紙は法務局内の印紙売り場で購入することができます。
郵送で取得
不動産は、土地や建物の所在地によって管轄する法務局が定められており、郵送の場合は管轄する法務局に対し、申請書、登記印紙、返信用の切手を郵送します。登記印紙は郵便局でも購入することができます。
取得の注意
登記事項証明書には、現在の状況のみが記載された「現在事項証明書」と過去の履歴も含めて記載されている「全部事項証明書」、すでに閉鎖された内容が記載された「閉鎖事項証明書」があります。それぞれに共同担保目録をつけることができますが、現在の有効な内容・抹消も含んだ全部の内容を選ぶことができます。
不動産取引の場合、取引履歴にも注意する必要がありますので、共同担保目録付の「全部事項証明書」をとることが一般的です。
閲覧の方法
誰でも閲覧することができます。閲覧と言えば「紙の資料を見て調べること」と思いますが、最近は登記内容がコンピュータに保存されており紙の登記用紙そのものがなくなったため、わざわざ登記内容をプリントアウトして「登記事項要約書」という紙が交付されるようになりました。
コンピュータ化されていない法務局では紙の資料を見ることになります。なお、登記事項要約書は閲覧に代わるものですので郵送で取得することはできません。
閲覧の注意
登記事項要約書と登記簿謄本(登記事項証明書)の記載内容はほとんど同じですが、登記事項要約書には作成年月日や登記官の認証文などがありません。そのため、通常、何らかの取引の際、確認書類として使われているのは、ほとんどの場合、登記簿謄本(登記事項証明書)であることに注意してください。
登記情報提供サービス
インターネットを利用して登記内容をリアルタイムで調べることもできます。ここで得られる情報は登記簿謄本(登記事項証明書)と同じですが、この情報をパソコンからプリントアウトしたものは登記官の認証文等がないため同等の効果はないことに注意してください。
※財団法人民事法務協会 |インターネット登記情報提供サービス
取得・閲覧の費用
取得・費用については改定される場合がありますので、必ず事前に確認してください。