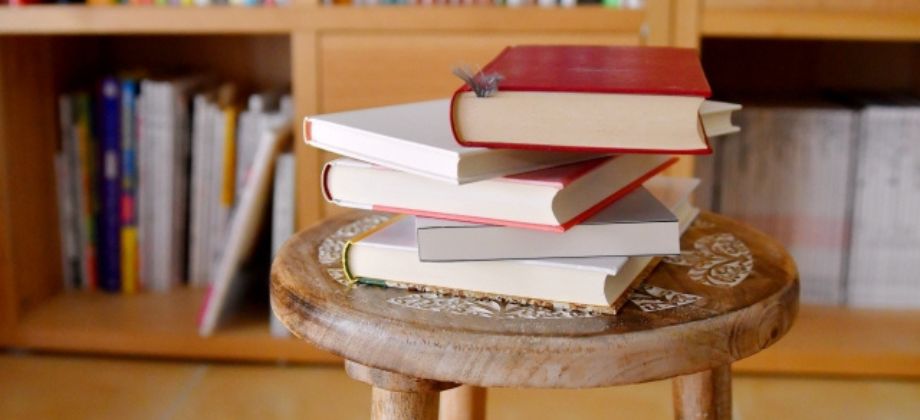「子どものピアノ練習の音が隣家に聞こえていないか不安…」
「夫のオンライン会議中、声が漏れていないか心配…」
そんな『音のストレス』を抱えるお客様のご相談があります。
ザ・ハウスにご相談いただいたA様(40代共働きご夫婦・小学生の娘さん)も「近隣に気兼ねすることなく娘にはピアノを思い切り弾かせてあげたい。防音対策に相談に乗ってもらえる工務店を探したい」というご相談でした。
A様が検討し取り入れたリアルな選択とともに、音問題の解決方法をお伝えします。
失敗しないポイント3つ!
・“誰にとっての音ストレスか”を具体的に想像する
・将来の暮らし方も見据えて設計する
・コストと効果のバランスを“体感”で確かめる
賃貸マンション時代に受けた苦情がトラウマに
賃貸マンションの5Fに住んでいたA様ご家族。ピアノを習い始めた小学生の娘さんは、毎日楽しく練習に励んでいました。ある時マンションの管理人さんから「ピアノの音がうるさいと苦情があるので解決してください」と言われトラウマに。そして戸建てを考えた経緯がありました。
3つの防音対策
ご相談を受けた工務店がご提案したのは、以下の3つの防音対策でした。A様はそれぞれの特徴やコスト感、生活への影響を比べながら、最適な方法を検討されました。
① 完全防音室をつくる
【メリット】
・高い防音性で、近隣への音漏れの心配がほぼなくなる
・時間を気にせず、いつでも練習できる
【デメリット】
・施工費が高く、専用の構造(浮き床、二重壁など)を要する
・音が外に漏れない分、家族の気配や会話も届きにくく、孤立感が出ることも
② 防音パネルなどを後付けする簡易対策
【メリット】
・コストが抑えられ、施工期間も短期間で導入できる
・音の響きが気になる場所だけに部分対応できる
【デメリット】
・完全な防音にはならず、隣家への配慮としてはやや不安
・内装に違和感が出る場合もあり、意匠性との両立が難しい
③ 家全体の間取り・構造を工夫して“音の逃げ道”をつくる
【メリット】
・家族の距離感を保ちながら、自然に音を軽減できる
・間取りの工夫で「音が響きにくい生活導線」を実現可能
・コストも調整しやすく、ピアノだけでなく生活音全般に効果的
【デメリット】
・初期設計段階での工夫が必要で、既に間取りが固まっている場合は対応しづらい
・対策が目に見えづらく、「本当に効果があるの?」という不安を感じる方も
・完全な防音にはならないので、近隣との関係性が良い場合に限られる
具体的な設計提案ポイントは5つ!
A様ご夫妻が話し合った末に選ばれたのは、③でした。専門的な防音室よりも「家族との距離を保ちながら、生活の中に自然に防音性を取り込む」という考えがあったからです。
そこで工務店から提案があった具体的な工夫ポイントは以下の5つでした。
●ピアノコーナーを“リビング内の一角”に確保
→ 家族の視線が届き、安心感を得られる配置。
●周囲の壁面に吸音材を仕込んだ造作壁を施工
→ 壁伝いに音が響きにくくなる工夫。
●隣家側には収納棚や水回りを配置して“音の緩衝帯”に
→ 家の外に向けた遮音のための構造的な工夫。
●窓は防音性能を重視し、二重サッシ+遮音ガラスに
→ 外への音漏れを大幅に軽減。
●床には音を吸収しやすい仕上げ材(コルクタイル)を使用
→ 反響音を抑えて演奏時のストレスを軽減。
このように「完全な防音室」ではなく、住まい全体で音をコントロールする工夫を選んだことで、多少予算はあがりましたが、防音室を作るよりもずっと予算は抑えられましたし、A様ご家族にとって無理のない範囲で理想的な防音環境が整いました。
マッチングコーディネータの視点!
音の悩みは図面では見えにくく、後回しにされがちですが、暮らしの満足度を大きく左右します。A様のように「防音室までは必要ないが、音には配慮したい」というケースは多く、対策の方向性を早めに整理しておくことで設計内容で音環境は大きく改善できます。
まずは、ご家族で「どんな音が、いつ気になるのか」を話し合ってみてください。それが防音計画の出発点になります。完全防音か、暮らしに溶け込む音対策か――選択肢は多様です。